「新卒初任給、30万円!いやいやウチは40万円台だ!」──2025年の新年早々、景気のいい話がそこかしこで聞こえてきます。各社がしのぎを削る“新卒争奪戦”において、もはや“月30万円台”は珍しくない時代へ突入しているのです。日々伝えられるニュースを見ていると、企業の好調ぶりがうかがえる…かのように思えますね。しかし、その裏側では、なんとも不気味で冷ややかな現象が同時進行しているのです。そう、早期・希望退職の急増という暗い影がひたひたと忍び寄っているのだとか。
特に、黒字を計上しているはずの大手企業であっても、構造改革やリストラ策の名目で45歳以上を中心に“人員削減”の大ナタが振るわれているというのだから、穏やかではありません。
今回は、新卒初任給アップの華やかな動きと、それをかき消しかねないほど急増する早期退職募集の実態を深掘り。さらに、公務員の給与水準や“就職氷河期世代”の待遇格差など、社会全体を覆う歪みについても迫ってみます。新しい時代を迎えた日本社会は本当にバラ色なのか、それとも…。どうか皆さん、心して読み進めてください。

東京商工リサーチによると、2024年に上場企業が発表した「早期・希望退職募集」は57社と前年の41社から約39.0%も増えました。さらに募集人員は1万9人と、前年の約3倍に急増したのです。その数は、2021年に1万5,892人を記録して以来3年ぶりの1万人超え。
「経営不振の赤字企業が人員整理をするのは仕方ないとしても、ここで目を引くのが“黒字企業”の多さです。黒字企業全体で8,000人超が早期退職対象になっているというから、まさに異常事態と言わざるを得ないでしょう。経営環境の先行きが不透明とはいえ、これまで働いてきた中堅~ベテラン層にとっては青天の霹靂(へきれき)です」(人事コンサルタント)
さらに2025年に入ると、ルネサスエレクトロニクスが国内外で社員約2万1,000人のうち5%未満を削減する方針を発表するなど、“人員削減”の嵐は止む気配を見せません。黒字決算にもかかわらず人員削減に踏み切る背景には「将来のリスクを見据えて、早期に体質改善を進めたい」という大手企業の思惑があるようです。

2024年に早期退職を実施した業種を見てみると、電気機器が13社と最も多く、次いで情報・通信業が10社。電気機器大手のコニカミノルタはグローバル構造改革に伴い、なんとグループ全社で2,400人を早期退職の対象としました。富士通も200億円ものリストラ費用を計上し、オムロンは1,000人、シャープはディスプレイ事業部門で500人規模を募集。リコーが1,000人、資生堂が1,500人といった具合に、錚々たる企業が名を連ねています。
しかも多くの企業が東証プライム上場で、直近決算でも黒字とあっては、中高年層の社員にとって寝耳に水。まるで“人材の選別”を一気に進めているかのような印象すら受けます。今や「会社は業績が良くても人を切る」時代だという厳然たる事実が、ここに浮き彫りになったのです。
こうして大手企業が容赦なくベテラン社員を“整理”する一方、新卒の初任給は華々しく上昇を続けています。ファーストリテイリング(ユニクロ)は大卒の初任給を33万円に引き上げると発表し、保険大手の東京海上日動火災保険は転勤・転居を伴う大卒初任給を来年4月には最大約41万円に。三井住友銀行も3年ぶりとなる初任給引き上げで30万円。メガバンクだけでなく、証券会社や建設会社、ノジマなどのサービス業でも30万円超えの企業が相次いでいます。
「これほどまでに新卒初任給が一気に上がったのは、やはり人手不足による“優秀な若手の争奪戦”が激化しているためです。ただし、中途採用やいわゆる“就職氷河期世代”への処遇改善はまったく追いついていない印象があります。その結果、『若年層だけが高給をもらえる』という不公平感が社内でくすぶり、遅かれ早かれ組織の分断を招くのではないか、と懸念する声が絶えません」(大手人事担当者)
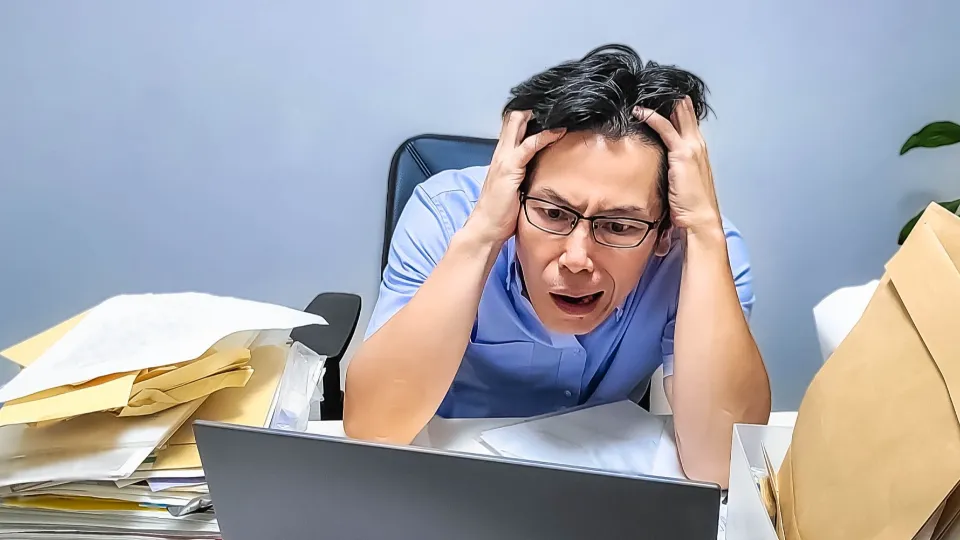
そもそも、新卒の初任給引き上げだけでは問題が解決しないことは明らかでしょう。ここ十数年、就職氷河期世代と呼ばれる40~50代前半の層は、若い頃から低賃金に甘んじてきました。現在の企業が新卒や若手社員にだけ手厚く賃金を引き上げれば、就職氷河期世代は「自分たちが損している」という思いを深くしてしまいます。もそも、新卒の初任給引き上げだけでは問題が解決しないことは明らかでしょう。ここ十数年、就職氷河期世代と呼ばれる40~50代前半の層は、若い頃から低賃金に甘んじてきました。現在の企業が新卒や若手社員にだけ手厚く賃金を引き上げれば、就職氷河期世代は「自分たちが損している」という思いを深くしてしまいます。
実際、「若手の賃上げ分のしわ寄せが中堅層やベテラン層に行ってしまう」ことが指摘されており、それが早期退職の誘い水になっている、という見方も。すでに人件費のバランスが危うくなるなか、会社が選ぶのは「今後さらに活躍の見込める若手」と「コストがかさむ中高年層」…と言えば、どちらを残そうとするのかは火を見るより明らかかもしれません。
こうした変動の波は民間企業だけにとどまりません。北海道十勝に目を向けて見ましょう。北海道がまとめた2024年4月1日時点の地方公務員の給与水準「ラスパイレス指数」によると、帯広市は5年ぶりの上昇で99.1をマークし、国の水準100に近づきました。しかし、ここ数年は国よりも低い水準が続いているため、人材確保のためにはさらなる改善が必要と見る向きもあります。
一方、町村部を見ると、13町村が上昇し5町が下降。最も高かったのは更別村で99.0、2位の足寄町は1.5ポイントも上昇しました。逆に芽室町は0.6ポイント下げて97.5。これらは役職配置のタイミングや大量退職などが大きく影響するといわれています。

公務員の給与は一見安定的に見えますが、人材流出が起きれば行政サービスに支障を来す可能性もあります。今後も国と地方の給与格差、さらには大都市と地方の格差が拡大すれば、自治体運営そのものが立ちゆかなくなる危険すらあるでしょう。
ちなみに、厚生労働省の令和5年「賃金構造基本統計調査」によれば、大卒新卒者の初任給はおおむね24万円前後、年に12カ月分で288万円程度。さらにボーナスを0〜2カ月分として試算すると280〜330万円あたりが平均的な“新卒年収”になるといいます。
しかし大手企業や外資系、一部のIT系企業などでは「30万円超え」「40万円近い」という例もざらで、上と下の“二極化”が進んでいるのが実情です。
「物価上昇や円安の影響を考慮すれば、月給30万円でも決して余裕があるわけではありません。若者にとっては、初任給の額面が上がっても、家賃や光熱費、通信費などコストが跳ね上がってしまい、結局は金銭的なゆとりはそれほど感じられないでしょう。しかも将来的に子育てを考えるなら、『就職氷河期世代』の親から十分な経済支援が受けられないケースもあり、格差がますます広がる恐れがあります」(経済ジャーナリスト)

ある経営者の本音がSNSで話題となりました。
「若手はすぐに辞めるかもしれない。高い賃金で釣り上げてでも、採用しなければ会社が回らないんだ!」
実際に、少子化で労働人口が減り続ける中、企業が生き残るためには“人材確保”が最優先課題です。けれども、一方で就職氷河期世代が尻拭いをさせられる形になっており、「全体的な賃金水準を上げなければ根本的な解決にならない」という声も強く上がっています。
「氷河期世代は子どもを育てている最中なのに、給与がなかなか上がらない。これでは教育費にしわ寄せがくるし、新卒と同じペースで賃金アップしてもらわないと不公平が大きすぎる」
こうした訴えをよそに、大手企業は新卒・若年層への投資を加速させるばかり。もちろん若い世代を厚遇すること自体は悪いことではありません。ただし「勤続年数が長い層を軽視すれば、企業全体のモチベーションダウンにつながる」というリスクが見落とされがちです。
結果、早期退職で大事なノウハウごと離脱されるような事態が起これば、それは会社の自殺行為と言っても過言ではないでしょう。

では、大手企業が目先の合理化を優先してベテラン人材を手放し、新卒ばかりに高い賃金を払うことで何が起きるのか?
「まず考えられるのは、生産性の低下です。会社に長年貢献してきた人たちが、早期退職の対象として切られれば、次代に引き継ぐべきノウハウも消失しかねません。さらに、中堅層の残ったメンバーも『次は自分が切られるかもしれない』という不安を抱えてモチベーションを下げるでしょう。また、新卒や若手だけが手厚い待遇を受けるとなれば、(中高年層には)不公平感が募り、職場全体で連帯意識が薄れる可能性もあります。結果的に高コスト体質の改善どころか、企業文化の崩壊を招きかねないのです」(同コンサルタント)
業績の良し悪しが激変する現代、日本企業が生き残るための一手として“構造改革”が叫ばれるのは必然かもしれません。しかし、それを理由に早期退職を募り、中堅・ベテラン層を大幅にリストラする一方で、新卒の初任給だけを急上昇させるというやり方が、本当に「持続可能な経営」につながるのでしょうか。
人口減少が止まらない日本においては、今いる人材をどう活かすかが勝負の分かれ目になるはずです。若手の確保と同時に、全世代で賃金水準を引き上げる努力が必要となるでしょう。そうしなければ、時間とともに社内外の軋轢が増していき、企業自らの首を絞める結果に至るのではないか──そんな声が、各方面からますます高まっています。
「早期退職」の波は、決して大手企業や特定業種だけの問題ではありません。地方自治体でさえ給与水準が流動的になり、人材の取り合いに拍車がかかっています。さらに、物価高や円安が進めば、企業経営の舵取りはますます困難を極めるでしょう。
「企業に頼らず、個人としてキャリアやスキルを磨いていくべき」という論調が近年増えていますが、中堅社員の多くは家庭やローンを抱えているため、すぐに転職やフリーランスへ舵を切るのは簡単ではありません。一方で、若年層は高い初任給を得ても、先行き不透明な社会に対する不安を抱えています。
あちこちで噴出するこの“ゆがみ”が解消されない限り、賃上げのニュースをいくら叫ぼうと、本当の意味で安心して暮らせる社会には程遠いように思えます。

2024年以降の日本社会は「初任給30~40万円」の華々しさと「早期退職1万人超え」の不気味さが同居する、まさに光と影が表裏一体の状況と言えます。
もちろん、若い世代への積極投資は将来への期待を繋ぐ要素でもあり、決して否定ばかりできるものではありません。しかし、中高年や就職氷河期世代の賃金が大きく取り残されたままでは、社会全体の活力を維持することは難しいでしょう。企業や行政が明確なビジョンを持ち、全世代の賃金アップを検討しない限り、いずれ“急増する早期退職”というツケが一気に回ってくるのかもしれません。
「これからは若手の時代だ」──その掛け声は刺激的で、希望に満ちています。だが、その陰で多くのベテラン社員が冷遇され、組織から去っているのが実態です。果たしてこのままで、企業の成長や日本の再生が実現できるのか…。無闇に楽観視するよりも、私たちが立ち止まり、冷静に考える時が来ているのではないでしょうか。
少し前、「日本の名目GDP、4位転落の公算大 23年ドイツが抜く」──こんな見出しのニュースが配信されました。「日本の2023年の名目国内総生産(GDP)がドイツに抜かれ、世界4位に転落する公算が大きくなった」というものです。
注目したいのは、GDPで日本を抜く勢いながら、ドイツ人の勤務時間は日本人よりも短いという点。ドイツの平均年間労働時間は1,371時間ほどで、日本の約3分の2程度。さらに法律で原則1日8時間を超えて働いてはいけないと決められています。それでいながら、彼らの年収は日本人の1.4倍。
そして、ドイツの単位時間当たりの労働生産性はなんと日本の約1.6倍にもなるとされます。短い労働時間と高い賃金を両立できている背景には、「労働者の権利をしっかり守る」という社会的風土はもちろん、職業訓練制度の充実や労働者自身のスキルアップへの強い意識も大きいようです。一人ひとりが高度な専門性や効率的な働き方を追求していることが、高い労働生産性を実現しているのです。

では、ドイツが体現するような“短時間労働でも高い成果を上げる”働き方を、日本人である私たちはどのように取り入れられるのでしょうか? そのカギとなるのが以下の2つのポイントです。
前述の通り、ドイツは労働時間の短さにもかかわらず、高い労働生産性を維持しています。その背景には、職業訓練の充実や労働者一人ひとりのスキルアップへの意識の高さが挙げられます。
日本でも、政府が掲げる「骨太の方針」の中で、リスキリング(=新しいスキルを学んで新しい仕事に活かすこと)の重要性が明確に示されました。リスキリングプログラムは助成の対象となり、安価で受けられる環境が整いつつあります。実際、ここ数年の間に会社主導で各種研修やプログラムが導入され、社員がデジタルスキルや専門知識を高める機会を得ている企業も多いのではないでしょうか。
こうした学びのチャンスを活かして、自身の業務効率を高めたり、新しい事業領域にチャレンジしたりしていくことが、生産性向上の一助となります。特におすすめは、プログラミングやデータ分析、生成AIなど、デジタル技術に関するスキルの習得です。これらは今後ますます需要が高まる分野であり、短い時間で大きな成果を出すうえでも役立つことでしょう。

ドイツでは、1日8時間を超えて働くことが原則的に禁止されているなど、労働時間管理が非常に厳格です。余計な長時間労働がないからこそ、限られた時間内に「集中して働く」というスタンスが徹底されています。
日本でも、労働時間をただ長くするのではなく、業務内容に応じてメリハリをつける発想が必要でしょう。具体的には、会議の短縮、ムダな残業の削減、テレワークやフレックスタイムなど柔軟な働き方の導入によって、集中力をいかに保つかが重要です。
さらに、労働者側も「時間内に終わらせる」ためのスキルセットやセルフマネジメントを身につける必要があります。クラウドツールの積極的活用や、コミュニケーション効率の見直しなど、チーム全体で“生産性向上”を共有して取り組むのがポイントです。
私たちの労働環境は、賃金アップとリストラの同時進行という歪んだ状況を抱えています。働き手が少ない時代だからこそ、高い賃金を出して“若手”を確保するのも一つの方法です。しかし、その一方で就職氷河期世代や中堅・ベテラン層が冷遇され、大切なノウハウが流出してしまうリスクも否めません。
ドイツのように“限られた時間内で効率的に稼ぐ”仕組みを意識し、労働者自身も継続的にスキルアップを図ることで、短時間労働と高い生産性を両立できる可能性があります。そして企業や行政側も、全世代の賃金水準を底上げするビジョンを掲げ、柔軟な働き方や職業訓練制度をさらに推進していくことが重要でしょう。
「初任給を上げる」「人材を入れ替える」だけでは決して解決しない問題が、私たちの目の前に山積しています。本当の意味で日本社会が再生を果たすためには、今こそ既存の常識や慣習を打破し、多角的な視点で改革を進めなければならないのです。
「これからは若手の時代だ」という言葉が、すべての働き手にとって希望に満ちたフレーズとなるためにも、短時間労働でもしっかり稼げる仕組みを整えつつ、中堅やベテランまで含めた全世代の賃金アップを実現できるかどうか。それこそが、日本が再び世界の舞台で存在感を示す