全国で人材不足が叫ばれる中、実際には中小企業の採用担当者の7割以上が他の業務と兼務しているという実態があるそうです。その結果、採用活動に十分な時間やリソースを割けず、課題が山積している状況が浮き彫りになっています。現状を踏まえ、採用担当者が直面する課題を整理し、成功への道筋を具体的なスキルや事例を交えて解説します。読者の皆様が採用活動に自信を持ち、効果的に進められるための一助となれば幸いです。採用担当者の適性チェックリストもあるよ!
そんな窮地の採用事情のなか、中小企業の採用担当者にとって、「求人を出しても応募が集まらない」「やっと内定を出せたのに、入社して数カ月で辞められてしまった」といった悩みは珍しいことではありません。特に、採用担当が専任ではなく、本業と兼任しているケースが多い中小企業では、何をどう改善すればよいのか分からず、ひとりで悩む担当者も多いのだそう。

中小企業の多くが直面する課題のひとつに、人手不足が挙げられます。東京商工会議所の調査によると、特に従業員規模が21人–50人の企業では深刻な人材不足が報告されています。さらに、少子高齢化が進む中、労働人口の減少により人材確保の競争は一層激化しており、大企業との有効求人倍率の差も年々拡大しています。
応募数が不足する主な原因は以下の通りです。
多くの中小企業では、採用業務が専任の担当者に任されることはなく、他業務との兼任が一般的です。その結果、採用戦略が後回しになり、計画的な採用活動ができていない企業も少なくありません。
Indeed Japan株式会社の調査によれば、採用担当者の72.4%が人事・採用業務以外の業務を兼務していると報告されています。また、別の調査では、採用業務の主担当者が「役員」や「管理職」で85%以上を占めており、これらの役職者が他の業務と兼務しているケースが多いことが示されています。これらのデータから、中小企業における採用担当者の多くが、採用業務を専任ではなく兼務で行っている現状が浮き彫りになっています。

採用担当者の多くが以下の状況に直面しています。
具体例として、ある小規模製造業の採用担当者は、日常業務の合間に求人票を作成し、応募者対応や面接を行っていました。しかし、採用活動に割ける時間が週数時間程度しかなく、結果として内定者のフォローアップが十分に行えず、早期離職が相次ぎました。このような状況が繰り返されることで、採用活動そのものへの意欲を失うケースも少なくありません。
また、採用プロセス全体の管理が属人的で、担当者が不在になると採用活動が停滞してしまうことも課題です。採用業務における効率化やシステム化が進んでいない企業では、こうした問題がより顕著になります。
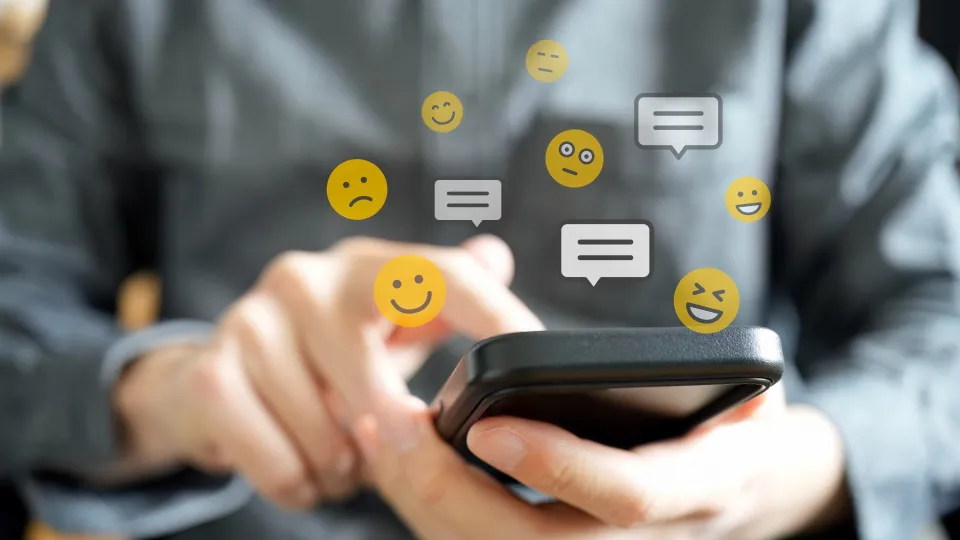
中小企業が採用競争で勝ち抜くためには、自社の独自性を明確にすることが重要です。ただ求人要件を記載するだけでは他社に埋もれてしまいます。以下のような点に注目しましょう。
近年、採用活動における情報発信力の重要性が増しています。採用サイトやSNSを活用し、ターゲット層に対して効率よく自社の魅力を伝える仕組みを構築することが求められます。
採用の成功には、適切な体制の構築が不可欠です。特に中小企業では、採用業務が調達活動のように捉えられる傾向がありますが、戦略的な取り組みが求められます。

採用業務を成功させるためには、以下のスキルが欠かせません。
応募者とのやり取りや社内の調整役として、スムーズなコミュニケーションが求められます。応募者に魅力を伝える力だけでなく、社員の声を拾い上げるスキルも重要です。
採用活動にはマーケティングの要素が含まれます。ターゲットとなる人材の特性を理解し、魅力を効果的に伝える戦略が必要です。
応募数や採用率、早期離職率などのデータを分析し、採用活動の課題を特定し改善策を立てる力が求められます。
採用活動は複数のタスクが並行して進むため、優先順位をつけて計画的に進めるスキルが必要です。
変化の激しい採用市場に対応するためには、新しい手法を取り入れる柔軟性と、現状を打破するための創造力が求められます。
採用担当者として適性があるかどうかを判断するために、以下のチェックリストを活用してください。多く当てはまる項目があれば、採用担当としての適性が高いといえます。
▢コミュニケーションが得意で、相手の立場に立って話を聞ける。
▢自分の考えを明確に伝えることができる。
▢データをもとに課題を発見し、解決策を考えるのが好き。
▢スケジュールをきちんと管理し、計画的に物事を進められる。
▢変化に柔軟に対応し、新しいアイデアを試すのが得意。
▢几帳面で細かなところにもよく気が付く。
▢ルールの決まった仕事を正確にこなすのが好き。
▢単純な作業の繰り返しが苦にならない。
▢自分自身で楽しみや価値を発見できる。
▢口が堅く、他人の秘密を守ることができる。
▢一生使えるスキルを身に付けたいと考えている。
▢仕事だけでなくプライベートも大切にしたい。
▢結婚しても長く仕事を続けていきたい。

ある地方の食品製造会社では、地元の食材を活用した商品開発が強みでした。しかし、知名度の低さから応募が集まらない状況が続いていました。そこで、地元のイベントやフェスティバルに積極的に参加し、製品のPRだけでなく、企業の魅力を地域に伝える活動を行いました。また、SNSで社員の日常や仕事の様子を投稿し、親しみやすさをアピール。その結果、地元での知名度が向上し、応募数が2倍に増加。地元出身の優秀な人材の確保に成功しました。
製造業を営む中小企業では、慢性的な人手不足に悩んでいました。そこで、社員の働きやすさを重視した制度改革を実施。週休3日制の導入やリモートワークの選択肢を拡充するなど、柔軟な働き方を取り入れました。また、これらの取り組みを採用ページで具体的に発信した結果、従来より幅広い層から応募があり、経験豊富な人材の採用に成功しました。
IT企業では、新卒採用した社員が早期離職する課題に直面していました。そこで、入社後の研修制度を見直し、OJTだけでなく外部セミナーやスキルアップ研修を取り入れることで、社員が安心して成長できる環境を提供しました。その結果、社員の定着率が30%向上し、採用コストの削減にもつながりました。
中小企業の採用担当者が抱える課題は、専任ではなく兼務で行う負担の大きさに起因することが多いです。しかし、独自の魅力を発掘し、情報発信力を高め、採用体制を整えることで、課題を克服する道が見えてきます。さらに、必要なスキルを身に付け、計画的かつ戦略的に採用活動を進めることで、優秀な人材を確保し、企業の成長を支えることが可能になります。
採用担当者が自信を持って活動できるよう、本記事が一助となることを願っています。